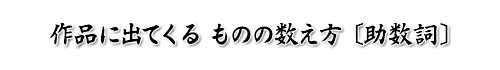 |
|
作 家
|
作 品
|
若山牧水 |
【夏の寂寥】 名も知れぬ誰やらが歌つた、 土用なかばに秋風ぞ吹く、 といふあの一句の、 荒削りで微妙な、 丁度この頃の季節の持つ『時』の感じ、 あれがひいやりと私の血の中に湧いたのであつた。 |
寺田寅彦 |
【夏目漱石先生の追憶】 暑休に先生から郷里へ帰省中の自分によこされたはがきに、足を投げ出して仰向けに昼寝している人の姿を簡単な墨絵にかいて、それに俳句が一句書いてあった。なんとかで「たぬきの昼寝かな」というのであった。たぬきのような顔にぴんと先生のようなひげをはやしてあった。このころからやはり昼寝の習慣があったと見える。 |
芥川龍之介 |
【アグニの神】 「私の主人の御嬢さんが、去年の春行方(ゆくへ)知れずになつた。それを一つ見て貰ひたいんだが、−−」 日本人は一句一句、力を入れて言ふのです。 「私の主人は香港(ホンコン)の日本領事だ。御嬢さんの名は妙子(たへこ)さんとおつしやる。私は遠藤といふ書生だが−−どうだね? その御嬢さんはどこにいらつしやる。」 遠藤はかう言ひながら、上衣の隠しに手を入れると、一挺のピストルを引き出しました。 |
芥川龍之 |
【戯作三昧】 馬琴は、「性に合はない」と云ふ語(ことば)に、殊に力を入れてかう云つた。彼は歌や発句が作れないとは思つてゐない。だから勿論その方面の理解にも、乏しくないと云ふ自信がある。が、彼はさう云ふ種類の芸術には、昔から一種の軽蔑を持つてゐた。何故かと云ふと、歌にしても、発句にしても、彼の全部をその中に注ぎこむ為には、余りに形式が小さすぎる。だから如何(いか)に巧に詠(よ)みこなしてあつても、一句一首の中に表現されたものは、抒情なり叙景なり、僅に彼の作品の何行かを充(みた)す丈の資格しかない。さう云ふ芸術は、彼にとつて、第二流の芸術である。 |
菊池寛 |
【蘭学事始】 彼らは、眉、口、唇、耳、腹、股、踵などについている符号を、文章の中に探した。そして、眉、口、唇などの言葉を一つ一つ覚えていった。 が、そうした単語だけはわかっても、前後の文句は、彼らの乏しい力では一向に解しかねた。一句一章を、春の長き一日、考えあかしても、彷彿として明らめられないことがしばしばあった。四人が、二日の間考えぬいて、やっと解いたのは「眉トハ目ノ上ニ生ジタル毛ナリ」という一句だったりした。 |
太宰治 |
【風の便り】 雨後の華厳の滝のところは、ただもう、にこにこしてしまいました。滝のしぶきが、冷く痛く頬に感ぜられました。お照も細く見えた、という結末の一句の若さに驚きました。女体が、すっと飛ぶようにあざやかに見えました。作者の愛情と祈念が、やはり読者を救っています。 |
夏目漱石 |
【ケーベル先生の告別】 ことに先生は自分の教えてきた日本の学生がいちばん好きらしくみえる。私が十五日の晩に、先生の家を辞して帰ろうとした時、自分は今日本を去るに臨んで、ただ簡単に自分の朋友、ことに自分の指導を受けた学生に、「さようならごきげんよう」という一句を残して行きたいから、それを朝日新聞に書いてくれないかと頼まれた。先生はそのほかの事を言うのはいやだというのである。 |
夏目漱石 |
【坑夫】 「そうとも、今からすぐ坑夫になって置きゃあ四五年立つうちにゃ、唸(うな)るほど溜るばかりだ。−−何しろ十九だ。−−働き盛りだ。−−今のうち儲けなくっちゃ損だ」 と一句、一句間(あいだ)を置いて独(ひと)り言(ごと)のように述べている。 要するにこのかみさんも是非坑夫になれと云わぬばかりの口占(くちうら)で、全然どてらと同意見を持っているように思われた。 |
作者不詳 国民文庫 (明治43年) 校訂: 古谷知新 |
【源平盛衰記】 忠盛零余子の枝を折進するとて、仰下し給ひし女房、平産して男子也、をのこごならば汝が子とせよと勅定を蒙りき。年を経ぬれば、若思召忘給ふ御事もや、次を以て驚奏せんと思ひて、一句の連歌を仕る。 |
ものの数え方・参考書 (Amazon)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
おすすめサイト・関連サイト…
スポンサーリンク
