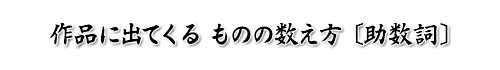 |
|
作 家
|
作 品
|
泉鏡花 |
【竜潭譚(りゆうたんだん)】 空よく晴れて一点の雲もなく、風あたたかに野面(のづら)を吹けり。 一人にては行(ゆ)くことなかれと、優(やさ)しき姉上のいひたりしを、肯(き)かで、しのびて来つ。おもしろきながめかな。 |
岡本綺堂 |
【青蛙堂鬼談】 その時分でも母などは何だか惜しいようだと言っておりましたが、父は思い切りのいい方で、未練なしに片っぱしから処分しましたが、それでも自分の好きな書画七、八点と屏風一双(そう)と骨董類五、六点だけを残しておきました。 |
梶井基次郎 |
【冬の蠅】 その火の色は曠漠(こうばく)とした周囲のなかでいかにも孤独であった。その火を措(お)いて一点の燈火も見えずにこの谿は暮れてしまおうとしているのである。 |
梶井基次郎 |
【ある心の風景】 しかしある夜、喬は暗(やみ)のなかの木に、一点の蒼白(あおじろ)い光を見出した。いずれなにかの虫には違いないと思えた。次の夜も、次の夜も、喬はその光を見た。 そして彼が窓辺を去って、寝床の上に横になるとき、彼は部屋のなかの暗にも一点の燐光(りんこう)を感じた。 「私の病んでいる生き物。私は暗闇のなかにやがて消えてしまう。しかしお前は睡らないでひとりおきているように思える。そとの虫のように……青い燐光を燃(もや)しながら……」 |
芥川龍之介 |
【侏儒の言葉】 宇宙の大に比べれば、太陽も一点の燐火(りんか)に過ぎない。況(いわん)や我我の地球をやである。 |
芥川龍之介 |
【寒さ】 踏切りの両側の人だかりもあらかた今は散じたらしかった。ただ、シグナルの柱の下には鉄道工夫の焚火(たきび)が一点、黄いろい炎(ほのお)を動かしていた。 |
芥川龍之介 |
【黒衣聖母】 第一これは顔を除いて、他はことごとく黒檀(こくたん)を刻んだ、一尺ばかりの立像である。のみならず頸(くび)のまわりへ懸けた十字架形(じゅうじかがた)の瓔珞(ようらく)も、金と青貝とを象嵌(ぞうがん)した、極めて精巧な細工(さいく)らしい。その上顔は美しい牙彫(げぼり)で、しかも唇には珊瑚(さんご)のような一点の朱まで加えてある。…… |
泉鏡花 |
【紫陽花】 少年はためらふ色なく、流に俯して、掴み来れる件の雪の、炭の粉に黒くなれるを、その流れに浸して洗ひつ。 掌にのせてぞ透し見たる。雫ひた/\と滴りて、時の間に消え失する雪は、はや豆粒のやゝ大なるばかりとなりしが、水晶の如く透きとほりて、一点の汚もあらずなれり。 |
若山牧水 |
【木枯紀行】 まだ二里近くも歩かねば板橋の宿には着かぬであらう、それまでには人家とても無いであらうと急いでゐる鼻先へ、意外にも一点の灯影を見出した。怪しんで霧の中を近づいて見るとまさしく一軒の家であつた。ほの赤く灯影に染め出された古障子には飲食店と書いてあつた。何の猶予もなくそれを引きあけて中に入つた。 |
国木田独歩 |
【たき火】 この時、一人の童たちまち叫びていいけるは、見よや、見よや、伊豆の山の火はや見えそめたり、いかなればわれらが火は燃えざるぞと。童らは斉(ひと)しく立ちあがりて沖の方(かた)をうちまもりぬ。げに相模湾(さがみわん)を隔(へだ)てて、一点二点の火、鬼火(おにび)かと怪しまるるばかり、明滅し、動揺せり。これまさしく伊豆の山人(やまびと)、野火を放ちしなり。冬の旅人の日暮れて途(みち)遠きを思う時、遥(はる)かに望みて泣くはげにこの火なり。 |
尾崎紅葉 |
【金色夜叉(こんじきやしや)前編】 多時(しばらく)静なりし後(のち)、遙(はるか)に拍子木の音は聞えぬ。その響の消ゆる頃忽(たちま)ち一点の燈火(ともしび)は見え初(そ)めしが、揺々(ゆらゆら)と町の尽頭(はづれ)を横截(よこぎ)りて失(う)せぬ。再び寒き風は寂(さびし)き星月夜を擅(ほしいまま)に吹くのみなりけり。 |
尾崎紅葉 |
【金色夜叉(こんじきやしや)前編】 宮は危(あやぶ)みつつ彼の顔色を候(うかが)ひぬ。常の如く戯るるなるべし。その面(おもて)は和(やはら)ぎて一点の怒気だにあらず、寧(むし)ろ唇頭(くちもと)には笑を包めるなり。 |
尾崎紅葉 |
【金色夜叉(こんじきやしや)前編】 さりとて今一つの請求なる利子を即座に払ふべき道もあらざれば、彼の進退はここに谷(きはま)るとともに貫一もこの場は一寸(いつすん)も去らじと構へたれば、遊佐は羂(わな)に係れる獲物の如く一分時毎に窮する外は無くて、今は唯身に受くべき謂無(いはれな)き責苦を受けて、かくまでに悩まさるる不幸を恨み、飜(ひるがへ)りて一点の人情無き賤奴(せんど)の虐待を憤る胸の内は、前後も覚えず暴(あ)れ乱れてほとほと引裂けんとするなり。 |
尾崎紅葉 |
【金色夜叉(こんじきやしや)前編】 彼はここに於いて曩(さき)に半箇の骨肉の親むべきなく、一点の愛情の温むるに会はざりし凄寥(せいりよう)を感ずるのみにて止(とどま)らず、失望を添へ、恨を累(かさ)ねて、かの塊然たる野末(のずゑ)の石は、霜置く上に凩(こがらし)の吹誘ひて、皮肉を穿(うが)ち来(きた)る人生の酸味の到頭骨に徹する一種の痛苦を悩みて已(や)まざるなりき。 |
尾崎紅葉 |
【金色夜叉(こんじきやしや)前編】 色を失へる貫一はその堪へかぬる驚愕(おどろき)に駆れて、忽(たちま)ち身を飜(ひるがへ)して其方(そなた)を見向かんとせしが、幾(ほとん)ど同時に又枕して、終(つひ)に動かず。狂ひ出でんずる息を厳(きびし)く閉ぢて、燃(もゆ)るばかりに瞋(いか)れる眼(まなこ)は放たず名刺を見入りたりしが、さしも内なる千万無量の思を裹(つつ)める一点の涙は不覚に滾(まろ)び出(い)でぬ。 |
夢野久作 |
【ダーク・ミニスター暗黒公使】 この少年の持物の全体を通じて何一つ上等でないものはない。そうして更に驚くべき事には、その服も帽子も、オリーブ色の雨外套(レインコート)も、染料の香気がまだプンプンしているらしい仕立卸しで、硝子(ガラス)のように光っているエナメル靴の踵(かかと)までも、たった今土を踏んだばかりのように一点の汚れも留めていない事であった。 |
田中貢太郎 |
【不動像の行方】 監物は藩主の一族で三万石の領地を受けて、藩の家老格に取扱われている者であったが、至って片意地の強いきかぬ気の男であったから、村役人の家の怪異なども別に気に懸けなかったが、それでも心の何処かに一点のしみを残していた。 |
ものの数え方・参考書 (Amazon)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
おすすめサイト・関連サイト…
スポンサーリンク
