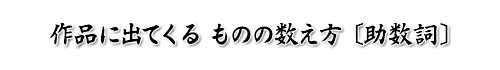 |
|
作 家
|
作 品
|
芥川龍之介 |
【あの頃の自分の事】 形式と内容との不即不離な関係は、屡(しばしば)氏自身が「雑感」の中で書いてゐるのにも関らず、忍耐よりも興奮に依頼した氏は、屡実際の創作の上では、この微妙な関係を等閑に附して顧みなかつた。だから氏が従来冷眼に見てゐた形式は、「その妹」以後一作毎に、徐々として氏に謀叛を始めた。さうして氏の脚本からは、次第にその秀抜な戯曲的要素が失はれて、(全くとは云はない。一部の批評家が戯曲でないやうに云ふ「或青年の夢」でさへ、一齣一齣(いつせついつせつ)の上で云へばやはり戯曲的に力強い表現を得た個所がある。)氏自身のみを語る役割が、己自身を語る性格の代りに続々としてそこへはいつて来た。しかもそこに語られた思想なり感情なりは、必然性に乏しい戯曲的な表現を借りてゐるだけ、それだけ一層氏の「雑感」に書かれたものより稀薄だつた。 |
太宰治 |
【道化の華】 なにもかもさらけ出す。ほんたうは、僕はこの小説の一齣一齣の描寫の間に、僕といふ男の顏を出させて、言はでものことをひとくさり述べさせたのにも、ずるい考へがあつてのことなのだ。僕は、それを讀者に氣づかせずに、あの僕でもつて、こつそり特異なニユアンスを作品にもりたかつたのである。それは日本にまだないハイカラな作風であると自惚れてゐた。 |
幸田露伴 |
【平将門】 悲劇はそこから生じて男は放蕩者(はうたうもの)となり、家は乱脈となり、紛争は転輾(てんてん)増大して、終に可なりの旧家が村にも落着いて居られぬやうになつた。これを知つてゐる自分の眼からは、一齣(いつしやく)の曲が観えてならない。真に夢の如き想像ではあるが、国香と護とは同国の大掾であつて、二重にも三重にもの縁合となつて居り、居処も同じ地で、極めて親しかつたに違ひ無い。若し将門が護の女(むすめ)を欲したならば、国香は出来かぬる縁をも纏(まと)めようとしたことであらう。其の方が将門を我が意の下に置くに便宜ではないか。 |
原民喜 |
【美しき死の岸に】 昨日も彼はリュックを肩にして、ある知りあいの農家のところまで茫々(ぼうぼう)とした野らを歩いていた。茫々とした草原に細い白い路が走っていて、真昼の静謐(せいひつ)はあたりの空気を麻痺(まひ)させているようだった。が、ふと彼の眼の四五米(メートル)彼方(かなた)で、杉の木が小さく揺らいだかとおもうと、そのまま根元からパタリと倒れた。気がつくと誰かがそれを鋸(のこぎり)で切倒していたのだが、今、青空を背景に斜に倒れてゆく静かな樹木の一瞬の姿は、フィルムの一齣(こま)ではないかとおもわれた。こんな、ひっそりとした死……それは一瞬そのまま鮮(あざや)かに彼の感覚に残ったが、その一齣はそのまま家にいる妻の方に伝わっているのではないかとおもえた。……農家から頒(わ)けてもらったトマトは庭の防空壕(ぼうくうごう)の底に籠(かご)に入れて貯(たくわ)えられた。冷やりとする仄暗(ほのぐら)い地下におかれたトマトの赤い皮が、上から斜に洩(も)れてくる陽(ひ)の光のため彼の眼に泌みるようだった。すると、彼には寝床にいる妻にこの仄暗い場所の情景が透視できるのではないかしらとおもえた。 |
泉鏡花 |
【木の子説法】 苦心談、立志談は、往々にして、その反対の意味の、自己吹聴(ふいちょう)と、陰性の自讃、卑下高慢になるのに気附いたのである。談中——主なるものは、茸(きのこ)で、渠(かれ)が番組の茸を 遁(に)げて、比羅(びら)の、蛸(たこ)のとあのくたらを説いたのでも、ほぼ不断の態度が知れよう。但し、以下の一齣(ひとくさり)は、かつて、一樹、幹次郎が話したのを、ほとんどそのままである。 |
宮本百合子 |
【我に叛く】 次第に、ゆき子の心持は、来なかったより悪いような有様になって来た。事は違っても、昨日と同じような種類の刺戟で、彼女の胸には、今までの蟠(わだかま)りが一時に甦って来たのである。この意識が起りかけた時、ゆき子は丁度、その小説の、最後の一齣にかかっていた。 |
ものの数え方・参考書 (Amazon)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
おすすめサイト・関連サイト…
スポンサーリンク
