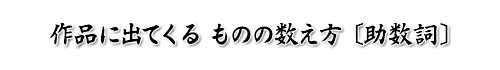 |
|
作 家
|
作 品
|
伊藤野枝 |
【転機】 それは何という荒涼とした景色だったろう! 遙かな地平の果てに、雪をいただいた一脈の山々がちぢこまって見える他は、目を遮るものとては何物もない、ただ一面の茫漠とした沼地であった。 |
北原白秋 |
【白帝城】 汪洋たる木曾川の水、雨後の、濁つて凄じく増水した日本ライン、噴き騰る乱雲の層は南から西へ、重畳して、何か底光のする、むしむしと紫に曇つた奇怪な一脈の連峰をさへ現出してゐる。その白金の覆輪がまた何よりも強く眼を射つたのである。 |
長塚節 |
【才丸行き】 遙かあなたには焦げたやうな一脈の禿山がつゞいて居る、山のこなたは左右の山と山との間がひろ/″\として居る、狹い間ばかり見て來た目には殊に心持がよく感ぜられた、一縷の烟も立たない三四十の萱葺の丈夫相に見える家が一つ所に聚つて居る、産土の森のやうなものも見える、 |
寺田寅彦 |
【コーヒー哲学序説】 すべてのエキゾティックなものに憧憬(どうけい)をもっていた子供心に、この南洋的西洋的な香気は未知の極楽郷から遠洋を渡って来た一脈の薫風(くんぷう)のように感ぜられたもののようである。 |
岡本かの子 |
【過去世】 さう云つて友はちよつと眉(まゆ)を寄せたが、友の内心には何処(どこ)かさとりめいた寛(くつろ)いだ場所が出来、一脈の涼風が過不及(かふきゅう)なしの往来をしてゐるらしくも感じられる。 |
泉鏡花 |
【海城発電】 頭巾(ずきん)黒く、外套(がいとう)黒く、面(おもて)を蔽(おお)ひ、身躰(からだ)を包みて、長靴を穿(うが)ちたるが、纔(わずか)に頭(こうべ)を動かして、屹(きっ)とその感謝状に眼を注ぎつ。濃(こまや)かなる一脈(いちみゃく)の煙は渠(かれ)の唇辺(くちびる)を籠(こ)めて渦巻(うずま)きつつ葉巻(はまき)の薫(かおり)高かりけり。 |
泉鏡花 |
【古狢】 「そっくりね。」 「気味が悪いようですね。」 と家内も云った。少し遠慮して、間をおいて、三人で斉(ひと)しく振返ると、一脈の紅塵(こうじん)、軽く花片(はなびら)を乗せながら、うしろ姿を送って行く。……その娘も、町の三辻の処で見返った。春闌(たけなわ)に、番町の桜は、静(しずか)である。 |
薄田泣菫 |
【利休と遠州】 「雲山と申しますのは、肩衝の名前です」 「肩衝? 肩衝といふと−−」老人の寂しい顔に一脈の火が点ぜられました。言葉にも何となく元気がありました。 |
芥川龍之介 |
【或日の大石内蔵助】 勿論当時の彼の心には、こう云う解剖的(かいぼうてき)な考えは、少しもはいって来なかった。彼はただ、春風(しゅんぷう)の底に一脈の氷冷(ひれい)の気を感じて、何となく不愉快になっただけである。 |
菊池寛 |
【恩を返す話】 肥後熊本(ひごくまもと)の細川越中守(ほそかわえっちゅうのかみ)の藩中は、天草とはただ一脈の海水を隔つるばかりであるから、賊徒蜂起の飛報に接して、一藩はたちまち強い緊張に囚われた。 |
ものの数え方・参考書 (Amazon)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
おすすめサイト・関連サイト…
スポンサーリンク
