|
 |
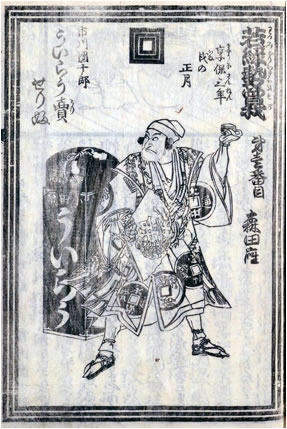 |
外 郎 売 |
 |
- 台詞が下から上へ流れます。文字がスクロールしている部分にマウスを乗せると動きが止まります。
- マウスを外すと再びスクロールが始まります。
- 漢字交じりスクロール版がこちらにあります ≫≫
*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
= このページでの表記についての解釈など =
2023年(令和5年)6月 2019年(令和元年)11月 2016年(平成28年)2月 2008年版改訂 みんなの知識 ちょっと便利帳 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
おすすめサイト・関連サイト…
スポンサーリンク
