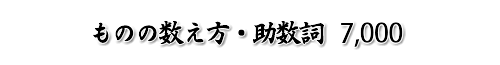《 コラム - ちょっと知識 》
船をなぜ隻と数えるのか。隻とは何なのか。
|
1. 船をなぜ隻と数えるのか
船をなぜ隻と数えるのか。
このことについて触れた一文がある。
宝暦11年〈1761年〉[今から264年前]
に、大阪の船匠、金沢兼光が表した日本と中国の船に関する百科事典的な解説書とされる『和漢船用集』の、「
艘 隻
之事」とする項に次のようにあり、『角川古語大事典(1987年刊)』では隻の項にこのくだりを収載する。
つまり、船を数えるのに隻や翼の字を使うのは、船を水鳥になぞらえて海が荒れた時にも沈まないように願うものであるとしている。
(※ 翼については後述)
ただし、原文全体を見るにこの根拠は希薄であるようにも思われる。原文は次のようにある。
このように、この一文では
艘
が船の総称であることや、船を数える語として使われること、また、隻も船を数える語として使われることを述べつつ、他にも船を数える語として、枝・葉・帆・柁・翼などをあげ、出典などを解説している。
その上で、『
凡
(全体を通じて・総じて・おしなべて・あらまし)舟の数に』としてまとめに入り、舟の数に隻・翼の字を用いることの理由を『水鳥になぞらえて』としているが、翼は別としても、隻は矢・魚・鳥・動物など種類の違う様々なものの数え方として使われており、隻を船に限って解説する根拠が薄いように思われ、この一文は様々な数え方があるという解説に重きを置いたものと理解すべきとも取れる。今後の研究に待ちたい。
2. 船を翼と数えることがあるのか
前掲の一文に「舟の数に隻翼の字を用ることは」との一節がある。では、船を翼と数えることがあるのだろうか。
この「和漢船用集」では、船を翼と数えることについて『
文選
』という文献を引き次のように記している。
※引用した「和漢船用集」では「翼は艘也」としているが、後述の「李周翰注」では「千翼、謂舟也」と、「舟」の文字が見られる。
このくだりに出てくる「文選」は、中国の詩文選集で六朝時代の梁の昭明太子の編。中大通2年〈530年〉頃の成立。「李周翰注
」は、開元6年〈718年〉に李周翰など5人の学者が共同で執筆した「五臣注文選
」の中の李周翰によるものという意味で、「文選」に注釈を加えたもの。
ここでは、船を翼と数える他の例と合わせて見てみる。
3. 船をなぜ翼と数えるのか
前項の通り、船を翼と数える例は中国の漢詩に見られたが、現時点では日本の文献では確認できていない。(調査中)
漢詩に見られるのは、西暦 307 年に没した張協の「三翼」と、西暦 530 年頃の「文選」という詩文選集の中の「千翼」で、前述のように古代中国には大翼・中翼・小翼と呼ばれるような軍艦があり、これらの形状から鳥の翼に船をたとえたのではないかと推測される。
例えば大翼の場合は、船の両側に大きく張り出した長い櫂にそれぞれ二人の漕ぎ手が付き、まるで鳥が飛ぶかのように川を進んだという。
このような姿から鳥にたとえ、数え方も「翼」とされたのではないかと推測される。(調査中)
4. 隻とは何なのか
現在、船を数える場合の助数詞に多く使われる「隻」とは何なのか。その成り立ちは何なのか。「隻」について、白川静の編纂による『常用字解[第二版]』(2012)で見てみる。
このように、
隻
という字は鳥と手の形の文字を組み合わせた漢字で、鳥を手に持つ形から鳥一羽の意味とされ、後に
雙
(双)の字が作られ、隻は対になるものの片方、また、一つのものを数える際にも使われるようになったとされる。
雙
は隹が二つと手の形で作られ二羽の鳥を手で持つことから一つがいの意。そこから対になるものの意として用いられる。
雙
の二つと、
隻
の一つを対比させた詩が『文選
』に見られる。
5. 古文書に見る「隻」
隻は成り立ちが鳥であることから、「斗酒隻鶏
」(一斗の酒、一羽の鶏)[後漢書/橋玄伝]などと鳥にまつわる言葉に使われる。また、
雙
(双)との関係から例えば
対
になった屏風の片方を
一隻
と数えるなど、対になっているものの片方を数えるのに用いられる。助数詞としては、「ひとつ」としての意味から船・矢・魚・動物など多くのものに用いられる。
この項では、どのようなものを数える際に「隻」が使われるかを古文書から見てみる。
なお、「隻」の読み方について振り仮名が振られた文献を見てみると、「一隻・いっせき」「一隻・いっぴき」「一隻・いっそく」「一隻・ひとつ」「一隻・かたわれ」「一隻・かた/\(かたかた)」「二隻・にわ」などが認められる。
6. 古文書に見る「艘」
船を数える際に使われる隻と艘のうち、隻は「ひとつ」とする意味を持つことから、船・矢・魚・鳥・動物など様々なものを数える助数詞に用いられるが、艘は「ふね」であるため専ら「船・舟」を数える助数詞として使われる。
「艘」がどのように使われるかを古文書から見てみる。
7.《参考》日本書紀の時代、「隻」「艘」は何と読まれていたのか
養老4年〈720年〉[今から1305年前
] に成立した『
日本書紀
』に、「船」の数え方として「隻」「艘」が見られる。では、これらは何と読まれていたのか。
『日本書紀』には読み方は記されていないが、鎌倉時代末期に表されたとされる日本書紀の注釈書『
釈日本紀
』では振り仮名が振られている部分がある。
それによれば、船の数え方に使われている「隻」「艘」には、「フネ」または「フナ」との振り仮名が振られ、「セキ」「ソウ」とする表記は見られない[国書データベース『釈日本紀』の358コマから383コマにかけての4箇所程 ]。なお、「隻」の字については「フサ」と振り仮名が振られている箇所があるが、これが「フナ」の間違いなのか、「フサ」とする数え方があったのかどうかは調査中。
(日本書紀での隻と艘の使い分けについては、その形状や用途などによるものなのかは調査中)
8.《参考》鮭などを一尺二尺と数えることについて
鮭などの魚を一尺(せき・しゃく)、一隻(せき・しゃく)と数えることがある。このことについて、江戸時代後期に書かれた『貞丈雑記
』に一文がある。『貞丈雑記』は、江戸時代中期の旗本(幕臣)・伊勢流有職故実研究家、伊勢貞丈
(享保2年12月28日〈1718年1月29日〉- 天明4年5月28日〈1784年7月15日〉)が、子孫への古書案内、故実研究の参考書として、宝暦13年〈1763年〉から亡くなるまでの22年間にわたり、武家の有職に関する事項を36部門に分けて記したもの。伊勢貞友、岡田光大らが校訂して天保14年〈1843年〉[今から182年前]に刊行された有職故実書。
『貞丈雑記』の一文を見てみる。
- 底本:古事類苑 P1572 動物部十八 魚下 〔国立国会図書館蔵 〕
- 新字体、現代仮名遣いとし、送り仮名の追加、及び適宜句読点を補うなどした。
ものの数え方・参考書 (Amazon)